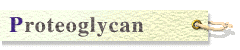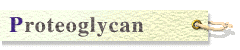|
| References | (1) | Hook M, Wasteson A, Oldberg A,Biochem Biophys. Res. Commun. 67, 1422-1428, 1975
|
| (2) | Nakajima M, Irimura T, Nicolson GL, J. Cell. Biochem. 36, 157-167, 1988 |
| (3) | Nakajima M, Irimura T, Di Ferrante N, Nicolson GL, J. Biol. Chem. 259, 2283-2290, 1984
|
|
(4) |
Vlodavsky I, Friedman Y, Elkin M, Aingorn H, Atzmon R, Ishai-Michaeli R, Bitan M, Pappo O, Perez T, Michal I, Spector L, Pecker I, Nature Med. 5, 793-802, 1999
|
|
(5) |
Hulett MD, Freeman C, Hamdorf BJ, Baker RT, Harris MJ, Parish CR, Nature Med. 5, 803-809, 1999
|
|
(6) |
Toyoshima M, Nakajima M, J. Biol. Chem. 274, 24153-24160, 1999 |
|
(7) |
Kussie PH, Hulmes JD, Ludwig DL, Patel S, Navarro EC, Seddon AP, Giorgio NA, Bohlen P, Biochem. Biophys. Res. Commun. 261, 183-187, 1999
|
|
(8) |
Fairbanks MB, Mildner AM, Leone JW, Cavey GS, Mathews WR, Drong RF, Slightom JL, Bienkowski MJ, Smith CW, Bannow CA, Heinrikson, RL, J. Biol. Chem. 274, 29587-29590, 1999
|
|
(9) |
Kramer RH, Vogel KG, Nicolson GL, J. Biol. Chem. 257, 2678-2686, 1982 |
|
(10) |
Nakajima M, Irimura T, Di Ferrante D, Di Ferrante N, Nicolson GL, Science 220, 611-613, 1983
|
|
(11) |
Vlodavsky I, Fuks Z, Bar-Ner M, Ariav Y, Schirrmacher V, Cancer Res. 43, 2704-2711, 1983
|
|
(12) |
Parish CR, Freeman C, Hulett MD, Biochim. Biophys. Acta 1471, 99-108, 2001
|
|
(13) |
Dong J, Kukula AK, Toyoshima M, Nakajima M, Gene 253, 171-178, 2000 |
|
(14) |
Hulett MD, Hornby JR, Ohms SJ, Zeug J, Freeman C, Gready JE, Parish CR, Biochemistry 39,15659-15667, 2000
|
|
(15) |
Vlodavsky I, Korner G, Ishai-Michaeli R, Bashkin P, Bar-Shavit R, Fuks Z, Cancer Metastasis Rev. 9, 203-226, 1990
|
|
(16) |
Gohji K, Hirano H, Okamoto M, Kitazawa S, Toyoshima M, Dong J, Katsuoka Y, Nakajima M, Int. J. Cancer in press
|
|
(17) |
Irimura T, Nakajima M, Nicolson GL, Biochemistry 25, 5322-5328, 1986 |
|
(18) |
Nakajima M, DeChavigny A, Johnson CE, Hamada J, Stein CA, Nicolson GL, J. Biol. Chem. 266, 9661-9666, 1991
|
|
(19) |
Saiki I, Murata J, Nakajima M, Tokura S, Azuma I, Cancer Res. 50, 3531-3637, 1990 |
|
(20) |
Mishima T, Murata J, Toyoshima M, Fujii M, Nakajima M, Hayashi T, Kato T, Saiki I, Clin. Exp. Metastasis 16, 541-550, 1998
|
| (21) | McKenzie E, Tyson K, Stamps P, Smith P, Turner P, Barry R, Hircock M, Patel S, Barry E, Stubberfield C, Terret J, Page M, Biochem. Biophys. Res. Commun. 276, 1170-1177, 2000
|
| | |
| |