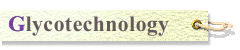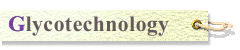|
| References |
(1) |
T, Murase, H, Ishida, M, Kiso, A, Hasegawa Carbohydr. Res. 188, 71,1989
|
|
(2) |
A, Kameyama, H, Ishida, M, Kiso, A, Hasegawa J. Carbohydr. Chem. 10, 549, 1991
|
|
(3) |
A, Hasegawa, HK, Ishida, T, Nagahama, M, Kiso J. Carbohydr. Chem. 12, 703, 1993
|
|
(4) |
H-K, Ishida, H, Ishida, M, Kiso, A, Hasegawa Tetrahedron: Asymmetry 5, 2493 (1994).
|
|
(5) |
K, Hotta, H, Ishida, M, Kiso, A, Hasegawa J. Carbohydr. Chem. 14, 491 (1995).
|
|
|
|
|
|