
Laurent博士は1930年SwedenのStockholmに生まれ、Karolinska Instituteで医学を修め、そこで1958年にM.D.を授与された。彼は1949年Endre A. Balazsの指導のもとで、その後Bertil Jacobsonのもとで研究し、1957年博士論文”Physico-chemical Studies on Hyaluronic Acid(ヒアルロン酸の物理化学的研究)”を発表した。Laurent博士は1950年代にKarolinska研究所の組織学および化学の講師を務めた後、BostonのRetina Foundationで4年間リサーチフェローおよび助手として過ごした。1961年助教授としてSwedenのUppsala大学に移った。1966-96年、同大学で医化学および生理化学の主任教授を務め、現在は名誉教授である。50年以上に渡って、彼はヒアルロン酸の物理化学的特性を研究し、その生理学的機能、代謝および病態時のヒアルロン酸の挙動の解明に貢献してきた。彼はUppsalaに結合組織生物学の学派をつくり、今では教え子たちの多くが彼の始めた研究を引き継いでいる。Laurent博士は、学術界でも多くの役職を歴任してきた。最近では、Royal Swedish Academy of Sciences会長(1991-1994)、Nobel Committee of Chemistry委員(1992-2000)、Board of Trustees of the Nobel Foundation議長(1994-2001)およびWenner-Gren Foundationsの科学部門委員長(1993-2002)などが挙げられる。
In Memory of Dr. Travard C. Laurent
著者は、50年以上にわたってヒアルロン酸の研究を続ける幸運に恵まれた。この間に、研究の方向性に決定的な影響を及ぼすような新しい技術の発展、発見そして概念を識別してこられたのは、素晴らしい体験だった。ヒアルロン酸研究の歴史を考える時、その成長・発展は、蓄積した経験の幹から、新しい枝が生える系統樹の形にたとえることができる(Fig. 1)。実際には知識のネットワークであるが、樹木に見立てたほうが、円滑に話を進めることができる*。
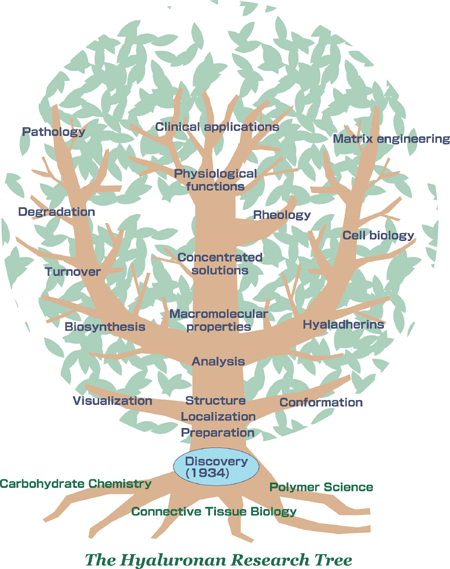
Fig. 1 ヒアルロン酸研究の系統樹
全ての研究は、既存の知識・情報から発展していく。我々の系統樹の根は、主に炭水化物化学、結合組織生物学および高分子化学に根ざしている。
ヒアルロン酸は炭水化物である!19世紀、炭水化物はCn(H2O)nの一般式で表される炭素の水和物と信じられていた。約100年前、元となる炭水化物の誘導体が確かに存在することがわかり、これらは炭水化物(単糖)ファミリーに分類された。「ポリマー」や「高分子」と言った用語は、分子量の決定に新しい技術が導入された20世紀初頭に定義され、多数の単糖から成り立つポリマーは多糖体と呼ばれるようになった。
組織切片の染色技術は19世紀に開発されたが、中胚葉由来の組織(結合組織)は、塩基性色素に染まりやすい細胞外無定形構造「基質」を持つことが多いことがわかった。その基質から炭水化物を含んでいるムコイドが抽出された。1889年、Mörnerが軟骨からムコイドを抽出した。これに含まれていた炭水化物は、のちに多糖体コンドロイチン硫酸と定義される。関連物質のヘパリンは、1916年McLeanによって抗血液凝固物質として発見され、続いてHowellが炭水化物と確認した。興味深いことに1918年、LeveneとLópez-Suárezがグルコサミン、グルクロン酸、硫酸を含む多糖を分離し、ムコイチン硫酸と名付けている。おそらくヒアルロン酸であったと思われるが、硫酸を含んでいると誤って仮定されたのであった。
ヒアルロン酸の発見以前に、Duran-Reynals(1929)が、「拡散因子」と名づけた精巣中のある生物学的活性について記述している。これをIndia inkと共に皮膚に注射すると、組織内でのインク粒子の拡散が増加した。この因子はのちに皮膚中のヒアルロン酸を分解する酵素、ヒアルロニダーゼであることが明らかにされた。
ヒアルロン酸の発見、分離調製、局在、化学構造および分析が、基本的知識の幹と言えよう。
1934年、コロンビア大学眼科学講座の生化学教室で研究していたKarl Meyer(Fig. 2)とJohn Palmerは、ウシ硝子体から分離した新しい多糖体を報告した。それはウロン酸とヘキソサミンを含んでいた。彼らはこれをhyaloid(硝子体)+uronic acidにちなんでヒアルロン酸(hyaluronic acid)と命名した。初めは酸として分離されたが、生理学的条件下では塩(ヒアルロン酸ナトリウム)のように挙動した。「ヒアルロナン(hyaluronan)」という名前は1986年、多糖体の国際命名法に従い導入された。

Fig. 2
Karl Meyer:ヒアルロン酸を発見し、構造を決定した。1977年撮影。同年Uppsala大学から名誉学位を授与された。
次の10年間で、Meyerと他の研究者たちは関節液、皮膚、さい帯、ニワトリのトサカ等から次々にヒアルロン酸を分離した。特筆すべきはKendall、HeidelbergerとDawson(1937)による発見で、グループA溶血性Streptococcus strainの莢膜多糖がヒアルロン酸であると同定されたことである。ヒアルロン酸の調製工程の原型は、まず変性あるいは分解によってタンパク質を除去し、その後アルコールまたはアセトンで多糖を沈殿させるという方法であった。卓越した改良がJohn Scott(Fig. 3)によって開発、導入された。陽イオンの界面活性剤(塩化セチルピリジニウム)を用い、塩濃度を変える分画沈殿法である。より洗練された電気泳動法やクロマトグラフィー法は、少量の調製にしばしば用いられる。
ヒアルロン酸の化学構造は、1950年代に事実上Karl Meyerとその研究グループによって解明された。彼らは、オーバーラップしたオリゴ糖を調製するためにヒアルロニダーゼを使い、それぞれのオリゴ糖は従来法で構造解析が可能であった。

Fig. 3
John Scott:塩化セチルピリジニウムあるいはアルシアンブルーを使うようにMrs. Ansethを説得しようとしているのだろうか?1977年撮影。
ヒアルロン酸の基本単位は、D-グルクロン酸とN-アセチル-D-グルコサミンがグルクロン酸のβ(1-3)結合でリンクした2糖である。この2糖単位はその後ヘキソサミニドβ(1-4)結合により糖鎖が直鎖状に伸長される(Fig. 4)。
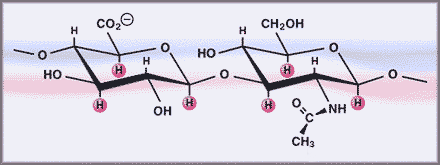
Fig. 4 ヒアルロン酸の構造
当初、ヒアルロン酸を定量的に分析する唯一の方法は、純化した形のポリマーを分離してその重さを計測するか、あるいはその単糖成分を定量することであった。ウロン酸はDisheのカルバゾール法で、ヘキソサミンはElson-Morgan反応で測定した(Zacharias Dishe, Fig. 5)。分析にはミリグラム量を要した。1970年に酵素法が導入されたことで次の段階が訪れる。他の多糖体や不純物があっても、ヒアルロン酸を測定可能な特定の生成物に分解できるようになったのだ。酵素法技術により感度が上がり、マイクログラム量での定量が可能になった。10年後には、Tengblad(Fig. 6)が、ヒアルロン酸に特異的な親和性を示すタンパク質(ヒアルアドヘリン)を使った技術を新たに開発した。これらのタンパク質はイムノアッセイに類似したアッセイ法で“抗体”として使われる。この新しい技術により組織中のヒアルロン酸をナノグラム量で直接的に定量することが可能となった。

Fig. 5
Zacharias Dische(左)はウロン酸決定のためのカルバゾール法−ヒアルロン酸研究の歴史上欠くことのできない技術−を考案した。Gunnar Blix(右)はグライコバイオロジーの先駆者で、シアル酸を発見した。1977年撮影。

Fig. 6
Anders Tengbladはヒアルロン酸に対して初めてラジオアッセイを考案した。これにより血清中や他の組織中のヒアルロン酸を測定することが可能になった。1981年撮影。
ヒアルロン酸の組織切片を可視化する新しい技術は、定量分析技術と平行して発展してきた。初期の頃から、トルイジンブルーのような塩基性色素による非特異的な染色法が用いられた。1960年代、John Scottは界面活性剤中でポリアニオンを分画した経験に基づき、アルシアンブルーを使った染色法の特異性を高めた。彼は塩濃度を変えることで荷電の異なる多糖体の分別を可能にした。1985年、親和性タンパク質を用いたヒアルロン酸の特異的局在性に関する最初の論文が発表された。この技術は現在、組織中のヒアルロン酸の局在を詳しく調べるために使われている。
細胞周囲のヒアルロン酸を可視化する独創的な技術が1968年ClarrisとFraserにより報告された(Robert Fraser, Fig. 7)。彼らが線維芽細胞の培養皿に粒子の懸濁液を加えたところ、粒子は細胞の隣接周囲から排除された。この排除はヒアルロニダーゼ処理で消失したことから、ヒアルロン酸によるものであることがわかった。このClarrisとFraserの方法は細胞/ヒアルロン酸の相互作用を見る生物実験において、非常に有用なものとなった。

Fig. 7
Robert Fraserはヒアルロン酸の代謝に関する先駆的研究業績により1988年、Uppsala大学より名誉学位を授与された。
ヒアルロン酸は電子顕微鏡によっても可視化された。1966年、FesslerとFesslerによって初めて判読可能なヒアルロン酸の画像が得られ、それは調製試料の平均分子量から予想される長さと一致する、線状に伸びた鎖であった。
分子構造解析には、直鎖の微細構造、つまり立体構造の研究も含まれる。立体構造を決める最初の試みは、30年前fiber diagrams(線維解析図)からのX線結晶解析によって行われた。1978年、John Scott(Fig. 3)により、過酸化物による酸化反応に対してヒアルロン酸の感受性が低いのは、ヒアルロン酸鎖分子内の水素結合のためであるという画期的な発見がなされた。10年後、この発見は核磁気共鳴を用いた分析で検証され、立体構造は1972年Atkinsによって示された2回軸らせん構造の模型と一致していた。
ヒアルロン酸の高分子としての特性研究は50年前に始まり、それを10年に渡って追究したのは、OxfordのAlexander G. Ogston(Fig. 8)、BostonのEndre Balazs(Fig. 9)そしてStockholmのTorvard Laurentがそれぞれ率いた3つのグループである。当初の主な問題は、分解あるいは他の修飾をすることなしに天然物中の多糖体を精製することであった。Ogstonは関節液からのヒアルロン酸を分離するのに限外濾過を使い、タンパク質が30%混じった標品を得た。他の研究者たちは種々の物理的、化学的および酵素的方法で調製し、タンパク質含量を数%にまで低下させた。しかしながら、物理化学的分析の結果全般から得られたヒアルロン酸分子の特徴は、一貫していた。多くの標品が多分散であったが、分子量は大抵数百万であった。光散乱法では、3〜400万の分子量のものは旋回半径が200ナノメーター程度のランダムコイルで、比較的固く、鎖状の分子として挙動することが示された。鎖の硬直性は、上述した鎖内の水素結合によるものである。ランダムコイル構造は粘度のデータと一致していた。Ogstonは沈降、拡散、流体力学的データを使い、分子は大きな水和した球体のように挙動すると結論づけた。これは、ランダムコイルの立体構造と一致する。

Fig. 8
Alexander G.(Sandy) Ogston−ヒアルロン酸の物理化学的研究の先駆者−1977年Uppsalaで楽器(ピアノ)に熱心に見入っているところ。同年Uppsala大学より名誉学位を授与された。

Fig. 9
Endre A.(Bandi) Balazs:ヒアルロン酸の医療応用の先駆者。1977年、著者の家で撮影。1967年Uppsala大学より医学の名誉学位を授与された。
最も大きなヒアルロン酸分子の立体構造が占める大きさから、分子は1g/lオーダーの濃度で完全に溶液空間を満たすと計算できる。それより高濃度になると分子は絡まり出し、溶液中でヒアルロン酸鎖は連続的なネットワークを形成する。絡まり始めの起点は、濃度をより上げた場合に急激に比粘度が上昇する変換点として、はっきりと見ることができる。
しかしながら、機械的な絡まりだけでなく、化学的な鎖−鎖間の相互作用(架橋)もネットワークを安定化させる。Ogstonはタンパク質が架橋剤として働く可能性を示唆した。すると、Dai Rees(1980)のグループがヒアルロン酸−ヒアルロン酸間の相互作用を証明するデータを発表した。10年後のScottによるヒアルロン酸の立体構造の研究では、ヒアルロン酸鎖は局所的に疎水性を呈し、疎水性の相互作用を通じて2ないしそれ以上の数のヒアルロン酸鎖を結合できることが明らかになった。
ヒアルロン酸ネットワークを含む溶液は著しい流体力学的特性—非常に高い粘着性、弾力性、そして強い剪断依存性—を示す。これらの特性は多糖体の分子量と濃度の複合関数である。たとえば、分子量400万の1%ヒアルロン酸溶液は、剪断率ゼロの時、水に対しておおよそ40万倍の粘度を持つ。より高い剪断率(1000/秒)では粘度はその値(40万倍)の1%に落ちる。振動粘度計の中で、溶液は高周波数では主に弾性体、低周波数では粘性体となる。最初の純粋なヒアルロン酸溶液の剪断依存性に関する研究はOgston(1951)によって、弾性に関する研究はJensenとKoefoed(1954)によって行われた。
多くの組織に起こりえる濃度でヒアルロン酸が絡まるという発見は、ヒアルロン酸が実際的に、連続的な三次元的な鎖のネットワークを通して生理的な活性を発現すると言う仮説につながった。これらのアイデアは1960年代にLaurentとOgstonの研究室で検討された。当たり前のことだが、流体力学的特性は潤滑と関係している。特に、ヒアルロン酸は常に関節内や筋肉−筋肉間のような可動性の組織を隔てる場所に存在することから、このことが言える。その他の特性は体液バランスと関係しているらしい。ヒアルロン酸溶液の浸透圧は濃度に強く依存し、したがってヒアルロン酸ポリマーは細胞外の水分量を制御する浸透圧緩衝剤として働く。
更にヒアルロン酸ネットワークは水の流れに高い抵抗性を持つので、組織間の流水に対してバリアを形成できる。ネットワークは、他の分子に対しても拡散バリアを形成する。高分子と粒子の動きはネットワーク中で妨害されるようになる。一方で、低分子化合物は比較的簡単に貫通できる。これらのバリアは生物学的に重要なのかも知れない。たとえば線維芽細胞を取り巻く細胞周囲のヒアルロン酸層は他の高分子や細胞との相互作用から、細胞を保護すると考えられる。またネットワークは機械的に他の高分子用の空間を排除するので(ゲルクロマトグラフィーは同様の排除効果)、組織中の種々タンパク質の濃度を制御することができる。この排除効果は、血管空間と細胞外組織空間の間のタンパク質分配と関連しているのではないか、また組織中の生理学的あるいは病的なタンパク質蓄積の駆動力となっているのではないかと議論されている。
1972年まで、ヒアルロン酸は組織中の不活性な化合物で、他の高分子とは特異的に相互作用しないと信じられていた。ところがその年、HardinghamとMuir(Fig. 10)が、ヒアルロン酸が軟骨中プロテオグリカンを会合させることを報告したのである。Hascall(Fig. 10)とHeinegårdは、ヒアルロン酸、プロテオグリカンのN末端球状タンパク質部分そしてリンクタンパク質が特異的に結合することを報告した。これは強固な会合であり、多数のプロテオグリカンは同一のヒアルロン酸に結合して軟骨や他の組織中で大きな会合体を作る。このようにヒアルロン酸は超分子構造を持つコンポーネントである。

Fig. 10
ヒアルロン酸が軟骨プロテオグリカンと会合するという発見は、ヒアルロン酸研究における転機となった。1977年のプロテオグリカンセッションで撮られた写真には、この分野の先駆者3人が写っている;左からHelen Muir、Tim HardinghamとVincent Hascall。
1972年にPessac、DefendiおよびWastesonらは、ヒアルロン酸を加えると、特定の浮遊細胞が凝集することを示した。これは、ヒアルロン酸が細胞表面と特異的に相互作用することを示した最初の報告である。UnderhillとToole(1979)(Bryan Toole, Fig. 11を参照)は、実際的にヒアルロン酸が、いかに細胞に結合するかを報告し、1985年にはその要因である“受容体”が精製された。その4年後、2つのグループがヒアルロン酸結合タンパク質としてリンパ球ホーミングレセプターCD44を同定したのに続き、UnderhillとTooleが見つけた受容体がCD44であることが明らかになった。それ以降、ヒアルロン酸を認識する他の細胞表面タンパク質が報告されるようになった。たとえばRHAMM(receptor for hyaluronan mediated motility:ヒアルロン酸媒介運動性のための受容体)、肝内皮細胞受容体、LYVE-1(lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor-1:リンパ管内皮ヒアルロン酸受容体-1)およびlaylinである。ヒアルロン酸と相互作用を持つタンパク質はヒアルアドヘリン(hyaladherins)と呼ばれている。

Fig. 11
Bryan Toole(左)はヒアルロン酸とヒアルアドヘリンの機能についての研究を立ち上げた。Bård Smedsrød(右)は肝臓の上皮細胞がヒアルロン酸をスカベンジすることを発見した。1985年St. Tropezの写真。
ヒアルアドヘリンが発見されるまで、ヒアルロン酸は物理的な相互作用を通じてのみ、細胞の挙動に影響を及ぼすと考えられていた。ヒアルロン酸が生物学的過程に関与しているかもしれないという根拠は全く状況的なものであり、大部分は生物学的過程におけるヒアルロン酸の有無からこの考えは構築された。推論の多くは非特異的な組織学的検討に基づいていた。大成功を収めた一連の研究が1970年代初め、Bostonで始まった。Bryan Toole(Fig. 11)とJerome Grossはイモリの足が再生する時、ヒアルロン酸はまず合成されたのち、ヒアルロニダーゼによって除去され、代わりにコンドロイチン硫酸が作られることを見出した。同様のパターンがニワトリ角膜の発生分化にも見られた。Tooleはヒアルロン酸の蓄積が組織中の細胞移動期に一致することを指摘している。この現象は非常に一般的なパターンであって、創傷治癒の場合にも認められる。
ヒアルロン酸受容体が発見されたことで、ヒアルロン酸が運動性といった、細胞の活性を制御する役割を担っているという概念の基盤はより確かなものとなった。この10年間で、細胞の移動、分裂、炎症、ガン、血管新生、受精等におけるヒアルロン酸とヒアルロン酸受容体の役割に関する多くの論文が発表されている。
ヒアルロン酸の生合成に関する研究は3つの段階を経てきた。第一段階の主役はAlbert Dorfman(Fig. 12)であった。1950年代初め、彼と彼の共同研究者たちはstreptococciを用い、ヒアルロン酸鎖に取り込まれる単糖の由来について報告した。しかしながら、無細胞系でヒアルロン酸合成を初めて証明したのは1955年のGlaserとBrownであった。彼らはラウスニワトリ肉腫からの膜分画酵素を使って、14C-標識したUDP-グルクロン酸をヒアルロン酸オリゴ糖に取り込ませた。Dorfmanの研究グループは続いてstreptococci抽出液から、前駆体であるUDP-グルクロン酸とUDP-N-アセチルグルコサミンを分離し、菌体の酵素画分を用いてヒアルロン酸を合成した。

Fig. 12
Albert DorfmanはChicagoのグループを率い、1950年代にヒアルロン酸の生合成の研究を始めた。1977年撮影。
第二段階では、ヒアルロン酸が他のグリコサミノグリカンとは違ったメカニズムで合成されるに相違ないことが明らかになった。ヒアルロン酸合成は硫酸化多糖と異なりプロテオグリカンの一部ではないので、タンパク質の合成を必要としなかった。合成酵素は菌体の原形質膜、真核細胞の形質膜に局在し、Golgi体にはなかった。合成装置は外部のタンパク質分解酵素に反応しなかったため、おそらく膜の内側に局在していると考えられた。しかし、細胞外のヒアルロニダーゼ処理でヒアルロン酸合成が促進されたことから、明らかにヒアルロン酸鎖は膜の外側に突き出ていた。結局、硫酸化グリコサミノグリカンと異なり、ヒアルロン酸鎖は還元末端に単糖を付加することで合成された。1980年代の真核細胞から合成酵素を分離する試みは、成功までに至らなかった。
1990年代初め、ヒアルロン酸合成酵素はグループA streptococci毒性因子であると考えられ、この情報を元に2つのグループ(Dougherty、van de RijnおよびDeAngelisら)がヒアルロン酸莢膜の産生に対しての遺伝子座を定義した。まもなく合成酵素はクローン化され、配列が決定された。脊椎動物からの酵素が発見され、わずか2 - 3年の間に多くの情報が蓄積された。合成酵素活性を制御するメカニズムは、今後の研究の重要な分野になるであろう。
1981年、ヒアルロン酸が正常血液中に存在し、末梢の組織からリンパ系で循環器系に運ばれることがわかった。この発見からMelbourneのRobert Fraser(Fig. 7)とUppsalaのTorvard Laurentの間でヒアルロン酸の代謝回転に関する共同研究が始まった。アセチル基をトリチウムで標識した微量の多糖体をウサギとヒトの血中に投与したところ、標識は2 - 3分の半減期で消失した。まもなくして、放射活性の大部分が肝臓に取り込まれ、そこでポリマー体は急速に分解されたことがわかった。オートラジオグラフィーからは脾臓、リンパ節、骨髄にも取り込まれていたことが判明した。細胞の分画から、肝臓内で取り込みを行う細胞は類洞の内皮細胞であることを論証でき、in vitroでの取り込み実験とin situオートラジオグラフィーの実験で確認された。これらの細胞は、他のヒアルロン酸結合タンパク質とはかなり異なるヒアルロン酸のエンドサイトーシスの受容体を持っている。多糖体はリソソーム内で分解される。肝の内皮細胞がヒアルロン酸をスカベンジすることがわかったのは、Bård Smedsrød(Fig. 11)の貢献による。ヒアルロン酸代謝の研究は他の組織でも行われ、今や我々は、生物における多糖体の大まかな代謝について正しい見識を持っている。
ヒアルロン酸分解に関して、もう一つの見解が最近注目されている。オーストリアのGüntherと、San FranciscoのRobert Sternと彼のグループの研究から、種々のヒアルロニダーゼの構造と性質が明らかにされ、これらの酵素の生物学的な役割に関する興味深い見解につながっている。
ヒアルロン酸の代謝の特殊性は、病的状態に関連している。長い間、関節炎のようなある種の炎症状態では、関節局所でヒアルロン酸が過剰生産されているらしいことはわかっていた。過剰生産は、中皮腫のような悪性疾患でも見られた。しかしながら、1980年代にヒアルロン酸の新しい分析技術が開発されて、初めてヒアルロン酸のレベルの違いを研究することに臨床的関心が高まったのである。血中の正常濃度が決定され、病気時、なかでも肝臓でヒアルロン酸が分解できない肝硬変時の濃度に注目が集まった。慢性関節リウマチでは朝の動作中に血中濃度が上がるため、“朝のこわばり”という症状が起きる。高濃度は、いろいろな他の炎症疾患時に、局所および血中の両者で認められた。臓器の機能不全は、ヒアルロン酸の局所的蓄積に続く、間質の浮腫によって説明できるかもしれない。
ヒアルロン酸を医薬品として開発をはじめたのはEndre Balazsにほかならない(Fig. 9)。彼は主概念をうち立て推進し、使用に耐えるヒアルロン酸標品を最初に作った人物である。そしてヒアルロン酸の工業生産を促し、多糖体の使用を世に広めた。
1950年代、Balazsは眼の硝子体の成分の研究に専念し、網膜剥離手術に使う代用硝子液の実験を開始した。インプラント(組織内注入)用ヒアルロン酸を使用する上で非常に大きな障害の1つは、炎症を引き起こす不純物を含まない標品の調製であった。Balazsはこの問題を解決し、そして彼の最終標品はNIF-NaHA(noninflammatory fraction of sodium hyaluronate)と命名された。1970年RydellとBalazsは関節炎を伴う競走馬の関節腔内にヒアルロン酸を投与し、臨床的に劇的な効果を認めた。その2年後、Balazsは動物およびヒト用のヒアルロン酸の製品製造を開始するようUppsalaのPharmacia ABを説得した。10年後には、MillerとStegmanがBalazsの助言に従ってプラスチック性眼内レンズ挿入時のデバイス(用具)としてヒアルロン酸を使い始め、ヒアルロン酸はHealon®の商標で眼科手術向けの主要製品となった。
以来、多くの応用が提案され、試行されてきた。例えば架橋ヒアルロン酸のようなヒアルロン酸誘導体は臨床的に使われてきている。種々の応用分野の中でも、眼科手術以外での粘性を利用した手術処置(visco-surgical procedure)の報告が多い。たとえば種々の組織インプラントとして、美容目的皮下注入や、あるいは音声改善のための弛緩声帯への注入がある。また癒着防止や創傷治癒促進用に、細胞移植時の坦体用や、薬剤の坦体として、さらに精子の分別のような細胞分離用の道具として等々の利用がある。他にも多くの応用が提案されている。
50年以上に渡って、系統樹に登り、どのように新しい小枝が幹から生えてくるかを見守る特別の立場に恵まれてきた。そしてそれらの新しく生えた小枝がたくましい枝に育つべく、太陽を浴び、正しい栄養を取り入れているか見てきた。日陰となり、成長が止まってしまった枝もある。系統樹がどの方向に伸びるのかを予測することは、常に難しい。我々のヒアルロン酸の樹は、空間や栄養を競い合うと同時に嵐から守ってくれる森の中で、他の系統樹にも、当然依存している。
未来の予測は難しいが、樹の上から見渡し、研究が我々をどのような方向に導くかを予言してみたい。私は臨床応用を樹の頂点に置いた。なぜなら、経済的なインセンティブが、資源を供給することにより、この多くの用途に使える多糖体の医薬品、あるいはその他分野の新規適応を目指した開発が進められる、と確信しているからである。ヒアルロン酸が、新しいタイプの粘弾性利用外科術や組織インプラントに使用が増大するであろうと容易に予測できる。今までのところ、こうした技術には、解明の進みつつある細胞表面のヒアルロン酸結合タンパク質に関する知識は、組み込まれていない。しかし、ヒアルロン酸マトリックスと個々の細胞の相互作用についてのより詳細な知識がそろえば、カスタムメイドの組織埋入品が作られるのも可能になろう。我々はこれをマトリックスエンジニアリングと呼ぶことができる。また、細胞移植の封入剤としてヒアルロン酸によるカプセル化が試行されるだろうことは、容易に予測できる。
ヒアルアドヘリンの知識が増えるにつれて、ヒアルロン酸が、たとえば細胞分別、薬剤ターゲティング、あるいは細胞保護のツールとして、受容体−リガンドの相互作用を利用した技術に使われることも予想される。その他の医療応用に関しては、各種病態におけるヒアルロン酸の挙動についての知識増加の上に成り立っている。我々は、ヒアルロン酸の蓄積で引き起こされる悪性浮腫を予防できるだろうか?臨床診断薬としてのヒアルロン酸アッセイの利用を広げることはできるだろうか?
当面の臨床応用の枝以外にも、現在2つのたくましく伸びる潜在性を持ったものがある。そこには我々がヒアルロン酸生物学を理解する上で鍵となる情報が含まれている。一つは、ヒアルロン酸合成酵素とヒアルロン酸分解酵素と、それらの制御についての究明が進めば、発生、創傷治癒、ガンのような生体系でのヒアルロン酸産生の増加や減少を調節できるようになるだろう。二つ目は、ヒアルロン酸受容体やその細胞内分子との相互作用に関する知識が増やせれば、それらの機能を、さらにはヒアルロン酸の機能を理解できるようになるだろう。